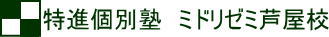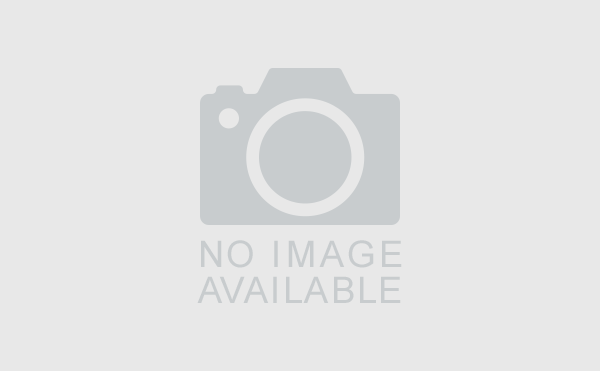落ちこぼれる受験をさせる親の不思議
受験生の親は考えない学校の常識
兵庫のトップ校の進学実績は、おおよそ上位3割で大阪公立大以上のの国公立大学、真ん中ぐらいで関関同立です。次のランクの高校では1割程度で大阪公立大学以上の国公立、上位3割で関関同立です。
この高校のランクは、高校入学時にはほぼきれいに上下関係にあります。ところが、最上位の公立高校の半数が、次のランクの高校の3割に差異学受験では追い抜かれる。こういう、上位の高校の中下位が下位の高校の上中位に追いつかれ、追い抜かれるという現象は、全国のあらゆる学校で例外なく起こっていることです「働きアリの法則/進学校で7割の生徒はなぜ失敗するのか?」。
ところが、この常識を親は考えずに「ひとつでも上の高校・中学」と目の前の受験に熱狂して、上位校に下位で合格させる。上位校の「京大・阪大・神戸大・大阪公立大100人!」しか見えてないから。自分の子供がそこには含まれていないとは考えないから。
学校間格差は埋まるが、学校内の格差は埋まらない
これまで書いてきたように、学校間の格差は自然に埋まります。上位校の速く難しい授業に多くの子供がついていけずに理解不足を起こす、あるいはそもそも上昇意欲がなかった子供の尻を叩いて無理やり入れたが高校では親の言うことはもう聞かなくなった、というような原因だと思います。あるいは、動物的な成長で、その子供の一番有利な時期が中学・高校受験であったということかもしれません。
でも、それだけで、この毎年何十万人単位で起こっている学校間の逆転劇を説明できるものでもない気がします。私も、この逆転劇の明確な説明は聞いたことがありません。でも、動かしがたい事実として起こっているわけです。
一方で、学校内では、中の上の子供が必死で頑張って上位に入って何とか神戸大というような多少の変動はあったとしても、下位の子供が200人以上ゴボウ抜きして上位に入ることはかなりレアなケースです。
ということは、受験は明確
ひとつ下の学校に上位で入れ!以外に正しい中学・高校受験はありません。学校の校風や指導方針など、それに比べたら微々たるものです。
オープンスクールに行って「あの学校の教育方針が気に入った」など言う前に、余裕を持ってA判定で進める学校に入ることです。この点をないがしろにして、オープンスクールに子供を連れまわす親など愚か以外の何物でもない。