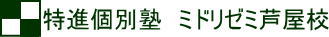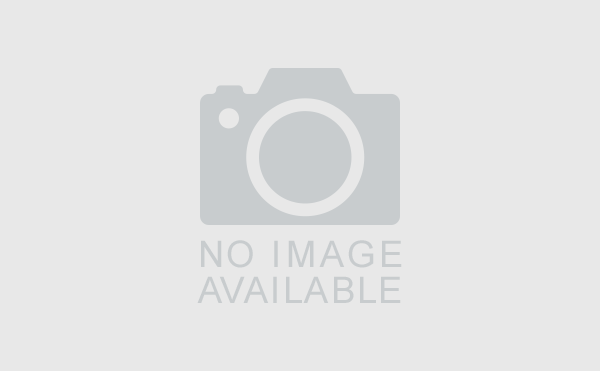2025 神戸大理系 数学 大問4~5の講評 後半/青チャートで解ける
前回の続きです。
大問4 空間ベクトル
(1)は簡単。教科書レベル
(2)は内積で普通に解けます。多少計算は面倒だが知れている。
(3)(2)が解ければ簡単に解ける。
大問5 数Ⅲ微積分
(1)は簡単に解ける
(2)はf(x)を一次式に変換して解くと面倒になる。h(x)ではf(x)のまま数Ⅲの距離の積分の公式に放り込んで∫√1+(f(x)’)^2(範囲1~t)にすれば簡単。
後はg(t)=h(t)+2を両辺微分して式を展開すれば解けます。
レベル的には青チャート、でもほとんどの生徒は解けない。その理由
そう難しくはないと書いてきましたが、ほとんどの生徒は解けません。仮にも神戸大学の理系の入試問題なんですから。ホイホイ解けたら神戸大学の値打ちはない。
ではなぜ解けないのか?
理由は簡単。解法を思いつかない以上に、計算力がないから解き切れないのです。式を見通して題意や変形の意図が分からないから、ほとんどの生徒は解き方を教えても自分で式を展開していけないのです。 これは、自力でどれだけ入試問題を解き切ったことがあるかという経験と自信がモノを言います。
ミドリゼミでは、チャート式が終わった生徒で、関関同立の理系や国公立の文系を志望する生徒に全員に数件の入試問題集をやらせます。ところが、多くの生徒は音を上げてこれをやり切ることができません。まだ入試問題を解いた経験のない生徒は解くのに1問1時間も2時間もかかることが多いからです。だから音を上げます。理由の一つは、この根性のなさです。そんな根性で神戸大に通るか~い!
2つ目は、こういう時間がかかる学習をする時間が取れないからです。ミドリゼミでは予習中心の学習で公立高校でも数ⅡBCは高校2年生の夏休みにはチャート式を完成してもらいます。理系では高3の春休みには数Ⅲを終了してもらいます。だから、その後共通テストの準備が始まる9月下旬までの間、たっぷりと時間をかけ入試勉強が出来るのです「上位国立大学に必要な学習・スケジュール」「神戸大学や大阪大学/上位国立大学合格への道」。
難問・奇問を解く必要はない
計算力だけでは対処できない、チャートにも載っていない難問奇問を出す大学もあります。大阪大学や京都大学が代表。それに同志社の今年の4問目「2025 同志社理系 数学の講評 大問4/合成関数の積分は難しい/ではどう合格するか?」。
でも、医学科でもない限り、こういう問題を解く必要はない。誰も解けないから。大学も見栄のために出題しているだけで、ボーダーライン上にいる受験生が解けるとは思っていないでしょう。そんなことは、まともに学習してきた受験生なら分かります。だから、入試でも捨てるんです。
自分と同じレベルのボーダーラインの生徒が解ける問題を確実に解き切る力が必要。それは解法を知っているだけではなく、計算力も大切な要素です。同時に共通テストで十分な合格圏を確保しておく必要があります。だから、受験までの学習プランが必要なのです。特に、数Ⅲを高校3年生まで持ち込む公立高校や私立では猶更です。早い目の予習して、高3の春休みまでには数Ⅲのチャートを完成させておかないと、共通テストも二次の準備も出来ません「経済格差は学力格差ははウソ。上位国立大学の理系では本当。でも一浪すれば埋められる。結局本人の資質次第。」。