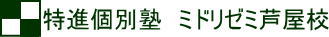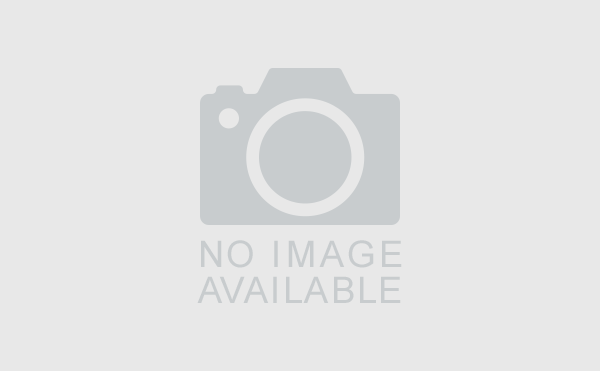古文は外国語、学習方法は英文法と同じ/学校の学習は薄すぎる
古文法の学習の重要性
古文など、多くの生徒にとっては英語より難解で分かりにくいものです。その理由は、難解な古文単語もありますが、中途半端に現代語と似ている助動詞や助詞が現代語の用法とまるっきり違うことにあります。おまけに、助動詞などはその上についている動詞などの活用によって全く意味が違っ来る複雑さあから、慣れなことには全く読めません。
おまけに、源氏物語などでは主語が省略されていて、動詞の主体がころころ変わるため、尊敬語と謙譲語の理解が出来ていないと、誰が誰んことを言っているのか全く分からなくなります。ところが、この敬語の巣類が多く、同じ敬語でも動詞と補助動詞で意味が違ったりしてとても複雑です。
というわけで、英文法と同等以上に文法の理解なしには、古文は読み取ることが出来ません。
ところが、学校の古文の学習は薄い
学校では、古文の文法を別枠で体系的に教えているところもありますが、多くは教科書の長文を読む中でその場その場で教わります。このような参考書は学校から配られますが、多くの学校では授業で使われることもなく、夏休みの宿題などで放り投げられるだけです。
だから、学校の先生のノートを丸暗記して定期テストでは良い点数を取れても、模試や入試などでには対応できない生徒が多くいます。ここを解消するのが塾の仕事です。

ミドリゼミの古文学習/文系
ミドリゼミではこういう問題集を高校1年・2年の夏休みまでに完成させるようにします。
この手のA4の大きさの問題集は何種類か出版されていますが、私は旺文社のこれがお気に入りです。内容は学校の参考書とほぼ同じですが、演習量が多いのです。
この程度の演習をしないことには、実際の文章で読み取る訓練にはなりません。その後は、このワンランク上の同じような問題集をします。こちらには長文読解も入って来ます。これで、後は入試問題集を解くだけです。

理系の古文への対応
古文はキチンと学習しようとすると結構な時間を取ります。正直、数学や理科の学習で文系より時間がかかる理系では十分学習する時間がありません。
おまけに、ザックリいうと、国立大学でさえ、共通テスト900点+二次900点の1800点満点で、古文の配点は50点しかなく、理系が多少頑張ったところで10点差がつくでしょうか?
そんなことをするくらいなら、数学で1問取れば楽勝で逆転で決まます。何しろ、こ理系の二次の数学は5問300点満点で、1問60点です。古文など学習する意味はないのです。
私立では3教科受験で古文など全く関係ありません。
ところがここで「推薦入試」というパワーワードが出てきます。でも、多くの学校で理系の上位大学に十分な推薦枠を持っている高校など私は知りませんし、自己推薦の枠も同様です。だから、古文も学習して全教科の成績を上げるなど、理系にとってはほぼ意味がないと私は考えています。そんなことを考える暇があれば、数学をやれ!
だから、学校の授業を出来るだけ熱心に聞いて、定期テスト前に見直して、それ以外はできないというのが私の考えです。もちろんこれは、大阪大学や神戸大学などの工学部などを目標にするミドリゼミの生徒の話で、共通テストでも9割以上取らなければいけない医学科などは別です。