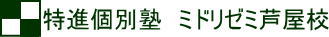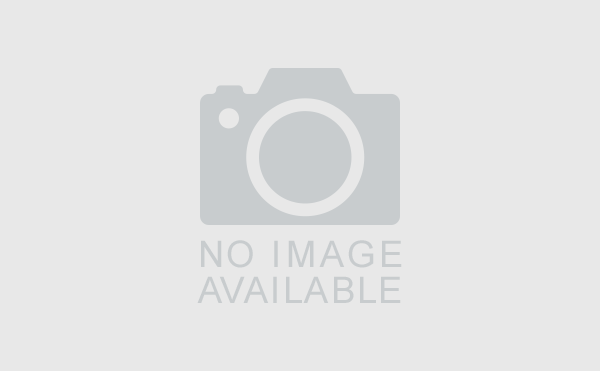進学校の下位が大学受験に失敗する理由/中学受験の前期入試で入学した悲劇/進学校で関関同立に合格できない悲劇
中学受験には前期と後期の入試があり、合格者の学力が違う
以前では中堅少し上の高校が中等部を作り、進学クラスなどをいろいろ作って進学校として再デビューすることが多くなっていました。学校の名称まで変えて、中堅高校のイメージを一新させて進学校再デビューの学校も珍しくありません。最近では、少子化の影響で小規模な女子大が廃校などになるケースが増えて、その付属の女子高が切羽詰まって共学化して進学クラスを作り出しました。
本来の意味の進学校は、これらの上のレベルの中高一貫校や私立高校を指していたのですが、こういう新規の進学校もそれなりの進学実績を出す学校も増えて、進学校の数は倍増したと言ってもいいでしょう。では本来なら進学校の下位に位置する新規校が有名大学への進学実績を叩き出している理由は何でしょう? 進学校の下位に位置するのですから、普通に考えればそういう進学実績を出せる生徒が集まるわけはないのです。
前期入試の第一志望で合格した生徒と、後期で上位校をギリギリで落ちてきた生徒では学力が違います。こういう新規の進学校で自慢げに宣伝する上位国立大学の合格実績は、第一志望などをギリギリで不合格になって後期入試で泣く泣くその学校に進んだ生徒が出していることが大きな理由です。授業の内容やカリキュラムに大差がある例、素晴らしい授業で進学実績があった例を私は知りません。ほとんどの場合、進学実績は集まっている子供の質に比例します。
いったん中学受験に足を突っ込み子供の尻を叩くと、進学校がダメだったからと公立中学に進む選択が、親の気持ちからも子供への体面からも出来ないから、以前は多くなかった後期入試が一般化して、本来ならその学校には来なかった生徒もかき集めることが出来るのです。
だから、前期試験で第一志望に滑り込んだところで、その学校が宣伝している進学先の大学には進めないわけです「進学校に入学しても落ちこぼれる最大の原因」。
明らかに違う上位と下位の学習
それでは、こういう前期入試で進んだ下位の生徒と後期入試で進んだ上位の生徒では、どう学習姿勢が違うのでしょう?
進学校の下位の生徒では、中学受験で学習塾で行っていたのと同じように、学校の宿題をしておけばいいのだろうと言う安易な学習を進めます。分からない問題は解答を書き写して分かった気になっています。彼らがこういう学習を続ける理由は、こういう学習方法で、厳しい中学受験を乗り切って第一志望の学校に合格できた自信があるからです。でもその学習というのは、本来なら中堅校に毛が生えた程度の学校にやっと合格できるものですが、進学校と名前を変えた学校への合格で自信を持っている本人はそれがわかっていません。
では上位の生徒の学習というのはどういうものでしょう?上位の生徒では分からない問題があると、自分で調べ考え、その上で「こういうことがわからない」と講師に説明を求めてきます。そして、説明を受けた後、その説明を写し書くのではなく、説明の理解を元に自力で解こうとします。
高校の学習で決定的になる格差
この両者では、学習が簡単で丸暗記の比重が多い中学の学習範囲ではまだそれほど大きなな差は開きません。ところが中学3年生ごろから高校の学習範囲に入ると、明確に差が出てきます。思考力が必要な高校の学習では、解答を書き写すだけの学習では通用するはずがないからです「進学校の下位、中堅公立高校で失敗するパターン/関関同立には絶対に行けない」。
ところが、彼らにそのことを伝えても、安易な丸写し・丸暗記学習から、自分で考えて自分で出来るようにする学習に切り替えようとはしません。もちろん後者の学習の方から厳しくしんどいからという理由も大きいでしょう。でも、もっと大きな理由は、「考えて自分でできるようにする」ということがどういうことなのかわからない進学校の生徒がとても多くなっているということです。
その理由は一番最初に書いたように、本来なら進学校に入らないレベルの子供が進学校と名前を変えた学校に入っているからにほかなりません。だから、こういう子ども学習指導や学習方法を教えるということだけで改善しようと言うことはとても難しいことです。非常に厳しい言い方ですが、まず資質という問題がその前に立ちはだかるからです。
中学受験は闇が多い
受験も言うに漏れずに、失敗者の話は拡散されず、成功体験のみ拡散されます。その上、子供が小さくかわいい盛りで、親は子供の可能性をキラキラと信じている。そこにインスタ映えのような受験の成功例と明るい将来を見せつけられ「あの学校に行けば」となる。
その親の気持ちを受験産業も学校も利用している。
このことに気づかずに受験にどっぷりと一旦ハマると「これまでの努力が・・・」となって撤退できなくなる。このことを受験産業は良く知っています。それに、中学の段階で築いたからと、公立高校受験をすることはできない。理由はレベルが低い公立中学に比べて調査書が悪くなるからです。学校間格差の調査書格差を補正してくれる高校受験は、公立高校はもちろん、私立でもありません。だから「高校から関学の付属にでも行かさないとヤバイ」と気づいても逃げようはないのです。
だから、疑問に思いつつも明るい面だけを見て中堅少し上の私立に通い続け、結果は公立に進むのと大差ないことになる・・・と言う例が多いと言うか、ほとんどです。