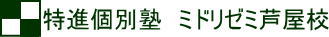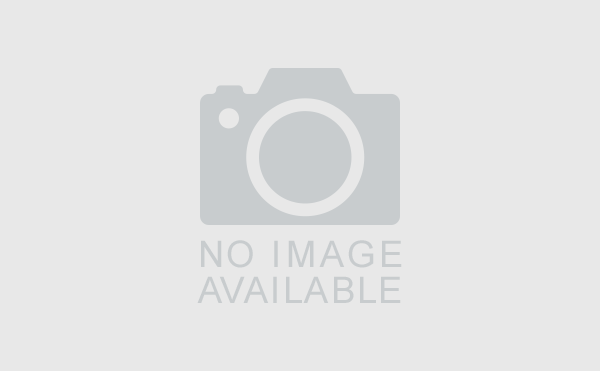共通テストの準備を始める時期です/できない生徒は関関同立も失敗する
9月の後半、遅くても10月の前半から共通テストの準備を始めましょう
やっとチャートなどの最終を復習し終わって今から入試問題を解こうとしている方はもう遅いです。その理由は簡単で今からは共通テストの準備を中心にした学習に切り替えないと、必ず共通テストで失敗するからです「上位国立大学に必要な学習・スケジュール」「共通テストが終わった。塾の生徒は合格基準点を取ってきた。その学習方法」「神戸大学や大阪大学/上位国立大学合格への道」。
共通テストは一科目60分から90分のテストです。だから、この過去問や対策問題を一科目やり、答え合わせをして、まちがいの内容を確認するのだけでも2時間はかかります。そこで苦手分野などが分かってその分野の対策を打つとなると1日とは言わずに2日3日仕事になります。
ということは1週間でできる共通テストの科目というのはせいぜい5教科程度のものなのです。もちろんこれと並行して二次テストの学習、あるいは今まであまり学習してこなかった副教科の共通テストの科目などの学習も進めなければいけないのですから5教科も難しいかもしれません。
したがって計算上は一ヶ月でせいぜい20教科の過去問題あるいは対策問題しかできないことになります。 20教科というのはたったほぼ2年分です。共通テストの模試を受けて実感されている方も多いと思いますが、共通テストは出題方式だけではなしに出題量も多く、独特の対策が必要になります。2年分だけではその対策が打てません。
指導経験上、7年分以上の過去問題や対策問題を行う必要がある
そのためには過去問や対策問題などでなるべく多くの問題に当たって、英語や国語の膨大な量の対策、数学などの時間配分で自分はどう対策していけばいいのか経験を積んで身に付けていくしかないのです。オークの教師や講師が「こう校受験すればいい」とアドバイスはするでしょうが、実際テストを受けながらそのアドバイスを実践できるかどうかというのは、経験で身に付けていくしかないからです。
そのためにはミドリゼミの経験上、7年分以上の過去問題や対策問題を積み上げていく必要があります。これだけの対策を打った生徒では共通テストで失敗してきた生徒はいませんが、それ以下だとやはり共通テストで思う通りの点数が取れない生徒が圧倒的に多いです。
最初にお話ししたペースだとこの7年分を積み上げるには、3か月以上の時間が必要です。だから共通テストの準備を行うには今の時期から始めないといけないのです。
この時期から共通テストの準備を始められない生徒は私立も失敗する
しかし、共通テストの準備が不十分で大阪大学や神戸大学に失敗しても、関関同立に滑り止めでひっかけばいいやと考えている方も多いと思います。ミドリゼミの経験上、そういう生徒のほとんどは関関同立も失敗してきます。
理由は簡単です。共通テストの準備を今からできないという生徒は、学力不足で今から国立の二次や私立の入試問題を解かなければいけないから準備できないのです。あるいはひどい生徒になると今からチャートで復習などをするから共通テストの準備ができないと言います。明らかに受験生失敗ですが、「神戸大がダメなら関学でも」と甘いことを言う生徒では結構多いです。
関関同立に受かる生徒はこの時期に共通テストなどに脇目も振らず私立の入試に必要な学習に専念しています。それだけの計画性があるのですから、この時期にチャートなどを復習する生徒は少ないです。関関同立に合わせた入試問題にチャレンジしているのです。そういう生徒より準備も少なく、しかも片足を共通テストの準備に置いている生徒がまともに太刀打ちができるはずがありません「共通テスト・センター入試で成功した生徒と失敗した生徒の差」。
だからこの時期に共通テストの準備も始められず、入試問題が難しいだのチャート式で復習しないといけないだの言う生徒は関関同立も失敗します。