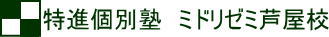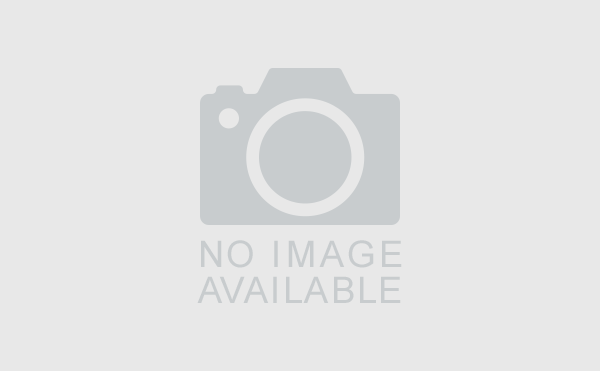共通テストの準備を3年の9月から始めるとはどういうことか?/1年生から綿密な学習計画が必要
この時期から共通テストの準備を始めなければいけない理由は? またそうするには?
独特の設問の英数国、それに問題量が多い英国などに慣れるため、自分なりの対策を考えるためには3カ月程度の準備期間が必要だとは、先日の「共通テストの準備を始める時期です/できない生徒は関関同立も失敗する」で書きました。
本日書く内容は、そういうスケジュールを組むには、1・2年生の頃からどう学習を進めていけばよいかということです。特に、学習進度が遅い公立高校の生徒には読んでいただきたいです。
共通テストの準備期間から逆算していく
3年の2学期から共通テストの準備をはじめることは、もうこの時期からは国公立の2次対策や私立の一般入試に向けて入試問題を解いて、チャート式などから入試レベルに学力を上げていく時間などないことを意味しています。3年の夏休みが終わった時期には、ほぼほぼ標準的な入試問題には対応できていなければなりません。共通テストは1科目60~90分解くだけでかかります。そして、その解答の確認や判明した苦手分野の復習などを考えると、数時間の以上、時には2~3日も1教科の学習にかかります。
二次対策などで、入試問題をゆったりと解いて学力を上げている時間などもはや残されていないのです。
それでは、3年生の夏休みに二次の標準的な入試問題を解ける状態に持って行くには、2年の夏休み、遅くとも2年の2学期には入試問題にチャレンジできるようになっていなくてはなりません。
中高一貫私立はいいが、公立高校の特に理系は厳しいスケジュールになる
だから、中高一貫私立は学習が簡単な中学高3年分の2年間で終わらせ、中学3年生から高校の分野に入るのです。それなら、文科系の英数国は高校1年生でほぼ全過程が終わることになります。理系でも高校2年生で数学も理科もほぼほぼ終わることになり、理系であっても予習気味学習を進めておけば上に書いたスケジュールが可能になります。
ところが、公立高校では高校に入ってから高校の学習を始めます。、まだ文科系では高校2年生の終わりに何とか英数国などは終わって、多少予習気味に進めていけば何とかなりますが、理系では主要科目の数学や理科が3年生の半ばまで学習がかかるので、学校で学び終えてチャートが何とかなるかなという時期から共通テストの準備が始まり、難しい二次の入試問題などに対応する暇もなく二次や私立の入試を迎えなければなりません。
だから、公立高校から理系の上位国立大学に進むのは、浪人しないと難しいと言っているわけです「国立大学の理系には公立高校から現役では難しい?/中学受験は必須」「国立大理系は公立高校から現役ではもうムリ?/理系なら中学受験は必須」。圧倒的に中高一貫の私立が有利です。
ところが、文系では、上に書いたようにそれほど公立の不利はありません「経済格差は学力格差の理系/でも文系志望なら公立も私立も関係ない」。
だから、ミドリゼミの高校の学習は徹底的に予習中心です
ほとんど鉄緑会の進度と同じくらいに予習を中心に進めます。1年生に入る前の春休みから英数を中心に徹底的に予習を進めます。基本的に1年の夏休み終了時には1年生の数学、英文法の基本、古文の基本は終わらせます。
2年生の夏休みには2年生の数学を終わらせ入試問題に入ります。理系なら加えて数Ⅲを始めます。、英文法の応用も終わらせ入試レベルの長文読解を開始します。古文も文法を終えて読解に入ります。このペースで学習しないと、3年生の夏休み終了時には標準的な入試問題を解ける学力を身につけて、2学期からは共通テストのじゅびを開始できないからです。国立大学受験の準備が出来ないからです「高校生の指導」「新高校生の新学期の開始/数学の予習を!」「ミドリゼミの夏休みの学習 高校2年生の数学/高校2年生の範囲を学習している私立の生徒の学習」「ミドリゼミの夏休みの学習 高校1年生/高校の範囲を学習している中学3年生」。
でも、これは、公立高校の理系志望者にはかなり無理な学習を強いることになります。だから、多くの公立高校の理系志望者には「中高一貫に対してハンデが大きすぎる。相手は中学受験で苦労しただから、キミはその分浪人覚悟で頑張らないと仕方がない。」ということも多いです。
この学習スケジュールについて来れない生徒は、全員関関同立目指して3教科の学習を指導します
このスケジュールについて来れない生徒の多くは、主要3教科の学力も十分ではありません。下手に共通テストの準備などに手を出すと、国公立だけでなく私立も間違いなく失敗します。だから、「関関同立に良ければいいと考えろ!」という指導をします。
もちろん、自分の学力や偏差値も考えずに、2年生になってもまだ「神戸大学」とか言って塾の指導を聞かない生徒も結構いますが、ほぼ全員失敗して関関同立も滑ってくることが多いです。