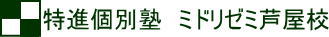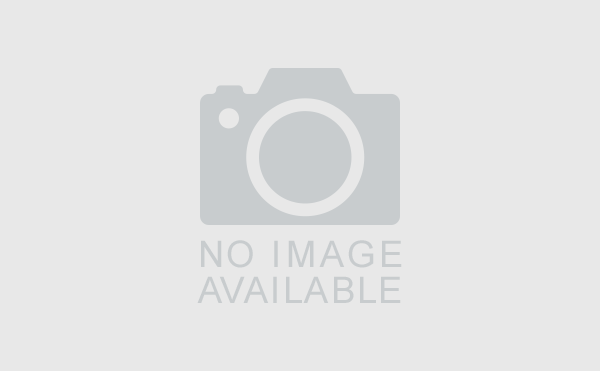共通テストの過去問や対策問題は何年分くらいするのか?
ミドリゼミの経験上8年分以上です
共通テストの過去問題をやり始めると、余りの点数の低さに多くの生徒は慄然とします。数学などでは、理解できないのではなく、時間配分を気にしてミスをしたり、時間配分や捨てる問題を間違えて得点を下げたりすることが多くの原因です。あとから考えてみれば簡単な問題だったということが多いはずです。
英語も同じような傾向です。多い問題量に焦ってミスをしてしまいます。国語では、その多い問題量にプラスして、何回というよりはあまりにもテクニカルすぎる選択肢になれずに「どちらでも同じやん」というようなことが頻発します。
これには、答え合わせをして反省し対策を打つことが必要です「共通テストの準備とは?/まずは過去問題!」。その反省や対策は2~3年分の問題をやって解決するものではありません。反省して対策を考えても思うように実際はできなかったり、その対策では不十分だったりを繰り返し、徐々に対応できるようになっていきます。予備校や塾で対策を聞いてパッと出来るようなものではありません。それは、運動などで「こうすればよい」とアドバイスを受けて意識してそう動作しても、実際はできておらず「違う、違う」と言われながら徐々に形になっていく過程と似ています。
そうこうして、2~3年分くらいは酷い点数を取り続け「このままでは落ちる1」と焦りながら、やっと5年分くらいをこなしているとコツが身に着き始め徐々に得点が上がってきます。
そうして、8年分くらいをして、初めて「こうしたらいいんだ」と実際に本番に自信をもって対応できるようになってきます。
だからミドリゼミでは9月の後半から過去問題を解き始めます
実際に過去問題を解き始めると、実際に解くのに1時間、答え合わせをして解き直して対策を考えるのにはその日だけでは足らない場合が、最初の頃はほとんどです。だから9教科1年分をするには2週間あっても最初の頃は足らないでしょう。もちろんこのペースは慣れるに従い、反省すること自体が少なくなり、問題点も把握しやすくなるに従い速くなります。しかし、8年分を終わらせるには3カ月の期間が必要です。二次対策や、9月ではまだ対策が不十分な副教科や情報の学習も進めながらなのですから。
だからミドリゼミでは9月中から共通テストの過去問題を解き始めます「共通テストの準備を3年の9月から始めるとはどういうことか?/1年生から綿密な学習計画が必要」。そのためには、3年生の夏休みには、志望大学の2次の問題をほぼほぼ解けるだけの学力を身につけていなりません。
だから、高校1年生から計画的に学習を進めることが必要です「上位国立大学に必要な学習・スケジュール」「共通テストが終わった。塾の生徒は合格基準点を取ってきた。その学習方法」「神戸大学や大阪大学/上位国立大学合格への道」。
このスケジュールは公立高校の理系の生徒には難しい
特に、公立高校から上位国立大学の理系を目指す場合、学校の授業は3年生の9月のこの時期でも数Ⅲや理科の授業を積み残していることが多いはずです。だから、文系より一層前倒しの予習が求められます。とても厳しい学習になると言っていいでしょう「国立大学の理系には公立高校から現役では難しい?/中学受験は必須」「国立大理系は公立高校から現役ではもうムリ?/理系なら中学受験は必須」。
だから、公立高校の生徒には数学が抜群に得意で明らかに理科系向きの生徒以外は、ミドリゼミでは文科系を進めます「経済格差は学力格差の理系/でも文系志望なら公立も私立も関係ない」。特に最近の高校生は浪人を嫌がりますから、文系の選択が賢明だと思います。