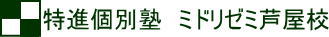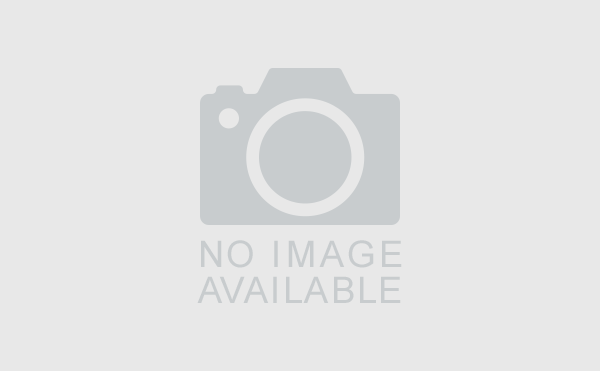共通テストや公立高校の入試問題で長ったらしい数学の文章問題の意図と評価/だからこそのミドリゼミの対策
Copilotと会話してみました。AIは出題者の意図を汲んで答える?
AIが述べる長ったらしい問題の意味と意図とは?
長い文章題の目的
1. 思考力・判断力・表現力の評価
- 文部科学省が掲げる「主体的・対話的で深い学び」に対応。
- 単なる知識の再生ではなく、情報の取捨選択・構造化・活用を問う。
- 実社会での課題解決能力を模した出題形式。
2. 文脈理解と論理的読解力の測定
- 長文の中に複数の情報(数値、条件、背景)が埋め込まれており、それを整理・抽出する力が必要。
- これは「数学的読解力」とも呼ばれ、数学的モデリングや論理的推論の前提となる。
知識偏重から、構造的理解と応用力へのシフト。その中で、数学は「抽象的な道具」から「現実を読み解く言語」へと位置づけが変わってきているのです。
AIが述べる教育評価における位置づけ
なぜ今、数学的読解力が重視されるのか?
- 従来の「計算力」中心の評価では、構造的理解や応用力が測れない。
- 社会の複雑化に伴い、文脈の中で数学を使う力が求められている。
- そのため、共通テストや入試では、長文・複雑な文脈・複数情報の統合が求められる問題が増加。
現在のテスト形式でこのような能力を評価することに対するミドリゼミの疑問
情報の抽出や論理的再構築はいいのですが、そのような整理・論理性を評価するテストとしては、問題数が多すぎ、時間が短すぎるのではないですか?結局は、似たような問題を解いた経験から丸暗記した論理的思考を引き出してコピーのように問題を解く能力が測られていると現状では思うのですが?
AIのお答え
おっしゃる通り、現在の共通テストや入試問題の構造には、「論理的思考力を測る」と言いながら、実際にはパターン化された処理能力を評価しているのではないかという矛盾が潜んでいます。以下にその構造的問題と背景を掘り下げてみます。
時間制限と問題数の構造的矛盾
1. 「深い思考」と「高速処理」の両立は不可能
- 長文問題は、情報の抽出・構造化・推論を要するため、本来は時間をかけて取り組むべきもの。
- しかし、試験時間は限られており、1問あたり数分で処理しなければならない。
- 結果として、受験生は「思考」ではなく「処理手順の再生」に頼らざるを得ない。
2. 問題数の多さが「読解の質」を犠牲にする
- 問題数が多いと、読解の精度よりもスピードが優先される。
- これは「読解力」ではなく「読解処理力」の評価になってしまう。
論理的思考の「コピー化」現象
1. パターン学習の支配
- 多くの受験生は、過去問や類題を通じて「このタイプの問題にはこの手順」というテンプレート的思考を身につける。
- これは「論理的思考の模倣」であり、本質的な論理構築ではない。
2. 構造理解ではなく「構造の再現」
- 本来の論理的思考は、状況に応じて構造を創出する力。
- しかし、試験では「既知の構造を再現する力」が評価されがち。
- つまり、創造的な論理ではなく、再生的な論理が優位に立つ。
なぜこのような設計になるのか?
制度的背景
- 大規模な試験では、採点の客観性・効率性が求められる。
- そのため、構造的に複雑な記述式や自由記述は避けられ、選択肢や定型解答に収束する。
- 結果として、「測りやすい論理性」=「再現可能な論理性」が評価される。
教育政策のジレンマ
- 文科省は「思考力・判断力・表現力」を重視すると言いながら、制度設計は依然として処理型評価に傾いている。
- これは、理念と運用の乖離であり、教育現場でもしばしば批判されている。
結論
この問題は、まさに「構造と評価の不一致」に関する問いです。恵造さんが重視されるような本質的な構造理解や創造的推論は、現在の試験制度では十分に評価されていない。むしろ、制度の都合によって「論理的思考」がテンプレート化され、コピー可能なものとして扱われている。
これは、音楽における「解釈の自由」が、録音やコンクールの採点基準によって「標準化」されてしまう現象にも似ています。つまり、構造の豊かさが、評価の枠組みによって矮小化されているのです。
ミドリゼミの対応
特に共通テストでは、このような数学的読解力からの論理構築がテンプレート化されている。短い時間で解くにはそのテンプレートを身につけるしかない本末転倒を乗り越える必要がある。したがって8年分以上の過去問題や対策問題を行うという、本末転倒の学習をします「共通テストの過去問や対策問題は何年分くらいするのか?」「共通テストの準備とは?/まずは過去問題!」「共通テストの準備を3年の9月から始めるとはどういうことか?/1年生から綿密な学習計画が必要」「共通テスト・センター入試で成功した生徒と失敗した生徒の差」「共通テストの準備はいつから始めるべきか?」。
そして、その対策に間に合うように高校1年生から計画的に学習をします「共通テストの準備を3年の9月から始めるとはどういうことか?/1年生から綿密な学習計画が必要」「上位国立大学に必要な学習・スケジュール」「共通テストが終わった。塾の生徒は合格基準点を取ってきた。その学習方法」「神戸大学や大阪大学/上位国立大学合格への道」。
でも、毎年思うこと
普段は詰込み学習で、テストだけ論理性や創造性を無理やり詰め込んで、詰込みの二次試験の対策に加えて、表面的な論理性丸暗記でしのぐ独特の共通テスト対策に2~3カ月使うので、生徒には物凄い負担がかかっている。
全て子供側に負担を押し付けている制度は腹が立つ。 本末転倒!