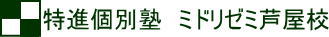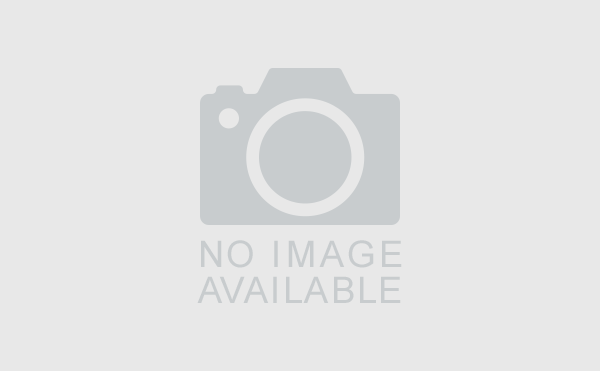公立校の皆さん、中高一貫私立用の教科書「体系数学」を誤解してませんか?
体系数学とは?
私立の進学中学校で一般的に用いられている数研出版の文科省の検定外の教科書です。数研の売り文句は「6カ年教育をサポートする。」です。
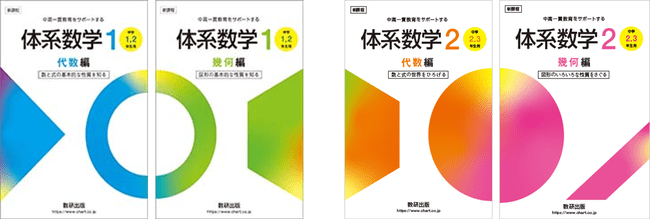
ご覧のように代数と幾何とがワンセットで、1・2があります。1は中学1・2年用、2は中学2・3年用です。
体系数学への誤解
では、この中学生用の教科書がなぜ「6カ年教育をサポートする。」などと説明されているのでしょう? 中高一貫校だからと中高の6年間使うわけでもないのにです。
その秘密はこの教科書の説明からうかがい知れます。「現行の学習指導要領では高等学校で扱う内容でも、中学校の内容と関連付けて扱った方が理解が深まると思われる内容については中学生向けのテキストで扱ったり、学習指導要領から削除された内容も必要に応じて扱う。」とこの教科書が説明されているからです。
だから、高校の内容にも踏み込んで中高の内容がミックスされたようなとても高度な内容を進学校の生徒は中学で学習しているとほとんどの方は思われています。
ブー!大間違いです。ほとんど高校の内容など書かれていません。中学の学習でも難しい発展問題や思考力が必要な高度な内容など書かれていません。「さすが、京大や阪大にいっぱい進む学校の教科書やわ~」ってなことはないのです。内容は公立の中学で使う文科省検定の普通の教科書と大差ありません。
では、何が違うのか?
違いは、中学3年間の学習を公立中学なら1・2・3年生用の3冊に分けて書いてあることを、この体系数学では「1・2年生用」「2・3年生用」と2冊に書いてあることぐらいだと言っても過言ではありません。
これは何を意味するのか?
数研は3冊の内容を2冊にまとめて、実質2年間で終わらせ、中3からは高校の学習を始めるように作っているのです。体系数学を使わず普通の検定教科書を使っている中高一貫の進学校でも、ほとんどの学校は中学2年生で3年分の3冊の教科書を仕上げて中学3年生から高校の数学の内容に入ります。」
私立の多くは中学の数学でも代数と幾何に分かれているので、この教科書を使えば中学2年生で中学三年分の学習を終えられるカリキュラム簡単に組めるのです。数研は私立の授業進度や時間割に合わせて教科書をまとめたに過ぎません。
だから、「6カ年教育をサポートする。」体系数学には進学校用に特別な内容が乗っていて、時には高校の学習内容ん踏み込んでいて、それを学べば学力が上がり、高校に入ってからの学習で凄く有利であるということではないのです。。
そんなものがあれば、数研も他の出版社や通信授業の企業も競って売り出すはずです。
この教科書が意味する「6カ年教育をサポートする」の意味
ということで、多くの中高一貫の進学私立では中学3年生から高校の授業が始まることが当たり前になっているということです。兵庫県下のトップクラスの中高一貫校では、中学3年間の理数系授業をほぼ1年間で終え、中学2年生から高校の学習が始まります。
ところが、これらの進学校でも、高校の範囲では通常の公立校とほぼ同じ速度で授業が進み、高1で数ⅡBCが終わり、高2で数Ⅲが終わります。
これは、中学の簡単な数学なら進学校に進むような生徒は3年分を1~2年間で終わらせるのは無理のない学習進度であるが、高校の難しい数学ではそうはいかないということです。私立の進学校はそんなことは百も承知だから、簡単な中学の学習をサッサと終わらせ、高校は通常ペースで学習し、大学受験までの1~2年間を受験勉強に専念できる期間を作り上げているのです。
だから、高校3年生で数Ⅲや理数系科目が終わり、チャートの理解もあやふやな状態で共通テストが迫ってくる理系では、公立高校の生徒は圧倒的に不利なのです「国立大理系は公立高校から現役ではもうムリ?/理系なら中学受験は必須」。だから、国公立の医学科などはほとんど私立のトップ校出身者ばかりで占められています「国公立大学医学科合格者は中高一貫私立ばかり」という新聞記事が出た/でもその理由までは書いていないので説明します」。
一方で文科系であれば、公立高校でも高校2年生でほぼすべてのカリキュラムが終わるので、理系のように圧倒的に不利ということはありません「経済格差は学力格差の理系/でも文系志望なら公立も私立も関係ない」。ここ大切です、算数の不得意な子供に中学受験などさせる意味はないということです。
じゃあ、理系なら公立高校は3年分を2年で駆け足で終わらせばいいじゃん!ってか? 名立たる進学校の生徒でも高校の学習は難しく、兵庫県下のナンバー2や3ランクの私立でも半数は落ちこぼれて関関同立がやっとです。神戸大学に進めるのは上位3割ほどです。2年間に短縮できるはずないじゃん!
この大学受験までを考えて中学の学習機関を短縮する私立の進学校の学習プランの現状が体系数学と言う教科書に表れているに過ぎない。数研が「新しい教育方法です!凄いっしょ?」と特別なことを中高一貫の進学校に提案している教科書ではありません。数研出版は中高一貫校の現状を織り込んで、内容を代数・幾何に分けて、2年間の学習で使いやすいように2冊分にまとめているに過ぎないのです。
一方で公立中学・高校では
私立の進学校が高校の数学を始めている頃に、公立中学の優秀な生徒は高校受験用の中学の難問対策をしているわけです。方程式の長ったらしい文章題など解いても高校の学習には全く役に立ちません「進学塾の最上位クラスで「神戸高校だ!」「北野高校だ!」と言っている中学2年生の皆さんへ/ライバルが何をしているか教えましょう」。
それで高校に入ってから、私立のライバルは高校の学習を終えて入試問題に取り組んでいるときに、「チャートが分からない」と言いながらクラブ活動に夢中なわけです。中学受験で大半の優秀な子供は、阪神間では私立に進みます。残った井戸の中で、自分たちのことしか分からない蛙となっているわけです。
高校受験を煽る大阪府のバカさ加減が分かるでしょう?
それを煽るように大阪府などが進学校用にわざわざ難しいC問題という高校入試問題を用意して、進学塾熱を煽っているのは本当にバカげたことです。特に、大阪府では英語で実質は英検2級で入試得点の代用が必要な状況にしています。当日のテストでは英検2級の見込み点を取るのはとても難しい内容になっているからです。
そしてこの英検2級は高校の学習範囲を学んでないと通りません。実質、大阪府の高校入試は文科省の学習要領からは逸脱しているのです。そんなことだったら、大学入試で著しく不利になる数学こそ数ⅠAの範囲を堂々と入試問題にしたらいいのです「大阪府公立高校のC問題入試のバカさ加減」。
そして高校1年生から数Ⅱを始めればいい。これをしないことには、無償化したところで公立高校に人気は戻らない。
だから、国公立の医学科がほとんど中高一貫の私立で占められる
公立高校のトップ校が高校3年生の半ばでやっと数Ⅲが終わり、大抵の生徒でチャート式の復習もキチンと終えていない時期から共通テストの準備を始めないといけません。学校の復習をしながらの学習で高偏差値の医学科に必要な共通テストの点数など取れるわけがない「共通テストの準備を3年の9月から始めるとはどういうことか?/1年生から綿密な学習計画が必要」。それに、共通テストが終わって二次試験までの1ヶ月で、チャートよりはるかに難しい入試問題を解けるようになるまで学力が上がるとお思いですか?
一方で、中高一貫の進学校では高校2年生では数Ⅲも終わり、高校3年生の1年間は全力で受験対策する。たとえ能力が同じだとしても、勝負にならないのです。そして、今の子供は「じゃあ、差の差を埋めるために浪人する」なんて気持ちもない。
だから「国立大理系は公立高校から現役ではもうムリ?/理系なら中学受験は必須」「国公立大学医学科合格者は中高一貫私立ばかり」という新聞記事が出た/でもその理由までは書いていないので説明します」となっているのです。
文系は体系数学も中学受験も関係ない、算数がホドホドの子供なら猶更です
一方で、上に書いたように、文科系であれば、公立高校でも高校2年生でほぼすべてのカリキュラムが終わるので、1年間は受験勉強に専念できます。理系のように圧倒的に不利ということはありません「経済格差は学力格差の理系/でも文系志望なら公立も私立も関係ない」。
更に言えば、算数の不得意な子供に中学受験などさせる意味はないということです。小学校の算数が出来ない子供が高校の数学ができるわけがない。中学受験で算数がホドホドの子供の尻を叩いて3番手レベルの私立に放り込んだところで、どうせ真ん中少し上の成績しか取れない。文系でも国公立レベルの数学に持ち上げるのは難しい。じゃあ、どっちみち関関同立が最上の進学先です。
3教科受験で数学もないのだから中学受験など子供を苦しめるだけで無駄だということです「中学受験塾、下位クラスの生徒/付属校に入れる以外道はなし」。