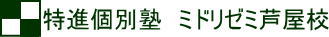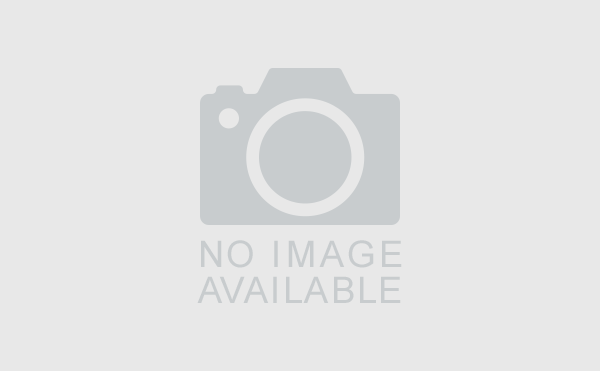数学と筋トレやスポーツの関係/出来ないことが同じレベルの講師を選ぼう
数学も筋トレと似ている/教えられる側の問題点
スポーツクラブなどでトレーニングしている方では、トレーナーから「こう筋肉を寄せるような感じで・・」と言われて、そう意識して力を入れてやってみるもののトレーナーから「違う違う」と言われた経験がある方も多いと思います。特に背筋のトレーニングなんかそうですよね! 私もそうです。ところが一方で、別に力を入れている様子もないのに「そうです~、よく出来てますね。」と言われているのを目にすると、とても釈然とできなくなります。
最初からできる人間と出来ない人間とでは関節の使い方や筋肉の使い方が違うのです。そしてできない人間に「筋肉を寄せるような感じで・・」などと抽象的なことを言われても、何をどうしていいのか分からない。「もっと具体的にどうすればいいのか教えろよ!アンタプロだろ!!」と愚痴りたくなります。
これとほぼ同じことが学習でも起こります。特に数学で起こります。ほとんどの生徒は、解答を読み、その解答の内容が「分かった」「分からない」と目の前のことしか理解できない。解答の裏にある「なぜそうするのか?」という解法にまでは頭が回りません。
そして、その解法を教えようとするとどうしても「この問題意図から、こういう基本問題のここが聞かれていることが・・・」という抽象的な解説になります。問題が高度化すればするほど「だからこうなるよね?」という暗黙知の伝達になる。
抽象的な解法のポイントを言葉で伝えるのですから、どうしても無理が出てくる。これが、「出来るヤツはできるが出来ないヤツは出来ない数学」という壁です。そして、レベルごとに「ここまでは理解できるだろうが、こっちは無理だろうな・・」という明確な壁があります。その壁を越えては、いくら長時間勉強しても上達しない。これはスポーツととてもよく似ている。
教える側の問題点
筋トレやスポーツではが「こうすればできるのに、なんでアンタは出来ないの?」とコーチによく言われることがあります。この関係は数学などでも当てはまります。最初から感覚的に理解できている人間が上達し、そして教える側に回るのですから、「どう動いているのか・考えているのか」という感覚的な感性を言語化して自己理解しようとした経験がない。そういう人間が教える側に回るのですから、教えること自体がムリゲーなのです「数学の解説が分からない理由/スポーツのインストラクターと同じ/数学を勉強しても成果が上がらない」「スポーツが習っても上手くならない理由/勉強も習っても出来るようにならない理由は同じ」。
でも、出来ないから苦労した人間は教えられるほど上達しないし、そもそも教えられるレベルにない。出来ない人間が感性の範囲にあることを自分で理解し言語化できて上達することは結構貴重なのです。もちろん、上に書いたように、レベルに応じてその言語化できる上限には限りがありますから、教えるのが上手いことと超難問をササっと解けることとは別のお話です。
先生や塾の選択
だから、生徒や親は自分の子供がどのレベルで、どういう人間に教わったらいいのかよく考えないといけません。少しデキがいいだけの常人が努力して入る大阪大学や神戸大学の志望者が、全部感性で解いてきた京大数学科出身の講師の解説を聞いても受け取るものがない。そういう講師と難しい授業を看板にしている予備校に行っても無駄なだけです。
先日、鉄〇会の春期講習に行っていた生徒が夜塾で復習をしているのですが、見事に何も教えられていない。いや、予備校側は教えているつもりなんでしょうが、この生徒の理解力とはマッチしていない。それは、その子にそういうクラスを用意した予備校の責任であると同等以上にそういうクラスに入れた親の責任でもあるわけです。
これと同じような状況は学校選びでも起こります。進学校では、いまだにこういう授業をして8割がたの生徒は理解できないようなことをする教師も多くいます。
私が言えるのは、自分の子供の志望校出身の講師を選ぶということです。同じ悩みを経験した可能性が高いからです。神戸大志望だからとより賢い京大の学生に教えてもらったら成績が上がると考えている親は、ダメ親です。メッシに教えてもらったら上手くなれる?そんなことを言うのは大バカ野郎です。子供の塾選びも失敗するでしょう。