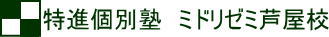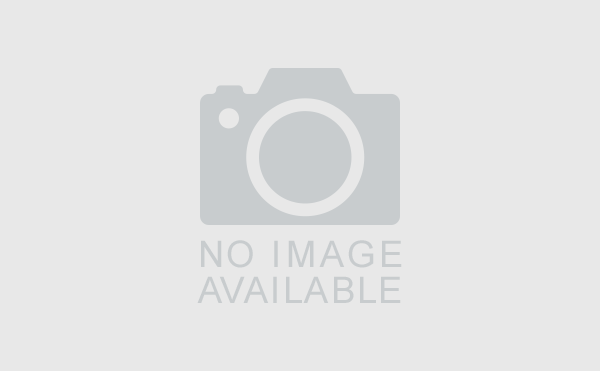2025 同志社理系 数学の講評 1~3のみ4はまだ/計算が面倒、でも難しくはない
日曜日の夜から気楽に始めたのですが、大問1で計算が面倒な問題が多く、2で本日は疲れて終了してしまいました。3番以後は後日報告します。
大問1は計算が面倒くさい!
問題はそれほど難しくありません。全問解きましょう。でも、計算がメッチャ面倒くさいです。計算ミスで多くの生徒が立ち浮かなくなったのでではないでしょうか。
(1)の確率の問題は特に難しくはありません。エの場合分けも単純。オで(1/3)^6(2/3)^kx6+k-1Ckが整理できるかどうかですが、難しくはない。
(2)のベクトルも取り立てて難しくはありません。まあ最後のコの問題で球の方程式を立てられるかどうかが勝負ですが、それほど難しくはない。
大問2
数列問題ですが、特に難しいことはありません。(1)(2)は教科書レベル。ただ(3)で階乗を使って答えを導けるかが勝負でしょう。教科書プラスアルファでは見かける数列ではありません。
(4)もan>0と書いてあるので答えを出すのは簡単です。ただ、帰納法などを使って証明してするのは面倒です。捨て問題だとしていいと思います。
大問3
微積の問題ですが、とにかく計算が面倒くさい。途中でブチ切れそうになります。ただそれだけです。
大問3まで
ここまでは問題の難しさより、計算量が必要です。大問1のような四則計算的なもの、大問3のような計算の工夫がいるものああります。
問題を解いていく限りは、制限時間内で合格ラインの6~7割を取れるように、面倒な問題をいかに飛ばすかと言うことが大切になると思います。大問1は(2)の子以外、大問2は全部、大問3は(3)の面積問題は飛ばす方が良いと思います。
取れれば十分合格する大学なので、捨てる問題をよく考える必要があると思います。