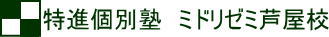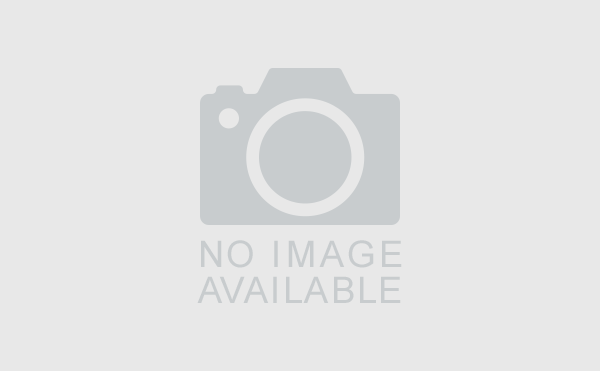最上位公立高校の中位は下位高校の上位に追い抜かれ、下位は中堅高校の上位に追い抜かれる/中高一貫の私立でも同じことが起こります/最上位校で落ちこぼれる生徒の特長
兵庫県内の高校の大学進学実情
我が塾の校区では、最上位校で神戸高校があります。その次が御影高校です。その下に葺合・芦屋高校などがあります。
この最上位校では、上位3割で神戸大以上の国立大学、下位3割で産近甲龍、その間が関関同立というような、おおよその大学進学になっています。
次のランクの高校では、上位1割程度が神戸大学以上、その次の3割で関関同立、真ん中ぐらいでは産近甲龍です。その下の中堅校レベルでは、上位の1割程度で関関同立、3割で産近甲龍という感じです。だいたいの目安ですよ「高校受験の志望校決定/ワンランクしたの高校の下位コースに最上位で入る」「大学入試で逆転する学校間格差・逆転は難しい校内格差/上位校に下位で進んではいけない理由/哀れさえ感じます」「進学校の中下位は、進学校に進学する意味がない/中下位の生徒に足を引っ張られる進学校」。
ということは、最上位校の真ん中の成績の生徒は、その下のレベルの上位の生徒に楽勝で追い抜かれますし、さらに下のレベルの高校の上位の生徒に追いつかれます。2ランクも3ランクも下の中堅高校の上位の生徒にさえ、最上位校の真ん中ぐらいの生徒では追いつかれるんです。
高校受験の段階ではこれらの高校は綺麗な階層関係にあります。最上位の高校ではほぼオール5,その次では通知簿4に5が混ざっているレベル、その下は中堅コーデは上位がオール4、下位では3と4が混ざっているレベルで、階段状にきれいに分布しています。
同様の傾向では中学受験で進む中高一貫の私立でも見られます。私が教えた中では兵庫県下でナンバー2で知らないものがいないほどの進学校である私立の中一貫校では、真ん中ぐらいの成績で大阪大学や神戸大学に進みます。下位では関関同立です。その下のレベルの有名な進学校レベルの私立中高一貫では最上位の公立高校と同じレベルで、上位で神戸高校以上、中位なら関関同立です。私立でも上位校の真ん中レベルの生徒は下位校の上位に追い抜かれます。
毎年毎年何十万単位で起こっているこの現象を説明した話は聞いたことがありませんし、話題にしている話も聞いたことがありません。だから中学や高校受験では一つでも上の学校に入ることが目標になり、上位校に下位で入学した生徒は落ちこぼれて悲惨な大学進学になっているのですが、そういうことを気にして中学高校受験をさせる親は少ないのが現実です。
ではなぜこのような現象が起こるのでしょう?
上位校の生徒が下位校の生徒に追い抜かれる理由1
上位校の生徒で成績がふるわないあるいは落ちこぼれている生徒を見ると、共通の要因があります。自分の学校の順位あるいは模試の偏差値ならどの大学に行くかという実感がないということです。
関関同立でD判定やE判定がつきながら、いつまでも神戸大学志望捨てない生徒が進学校には多い。それでは現実を受け入れ反省して、必死で学習に取り組むのかというとそうでもない。クラブ活動を楽しみ、学習時間も確保せずに成績が上がらないやり方の学習を漫然と続けます。塾で、「数学がそこまで落ちこぼれて行っては改善はもう難しいから、英語や古文の学習に絞って関関同立を目指すのが現実的で一番賢明なやり方だ。」と説得しても、「進学校のオレ様に何言ってるんだ。」というような調子で聞く耳など持ちません。
こうゆう生徒では、高校の学習範囲に入り学習内容は中学時代よりはるかに難しくなり科目数も増えているのに、それに適用した学習をせずに中学の学習と同じような調子で宿題をしている生徒が多いです。上位校に入るような生徒にとって中学の学習は難しくありません。学校の宿題や塾の宿題をして、分からない問題があれば回答を丸暗記していれば良い成績が取れていたのです。ところが難しくなった高校の学習では自分で考え自分で理解する学習と時間が必要です。
そういう学習方法にも適応せずに、考える時間も取らずに中学時代と同じような学習を進める生徒が非常に多いです。その上、中学や高校受験での成功体験があるから、塾で注意しても自分のやり方を変えようとしません。
中には間違った学習方法を続けて、熱心に丸暗記をして長時間学習をしてる割には、まったく成果が上がらない生徒も多いです。数学でも英語でもポイントを自分で理解せずに、書かれていることを丸読みにして問題を解いているだけだから、同じような問題がそのページに並んでいる問題集は解けても、ごっちゃ混ぜで出題されるテストでは解けないのです「進学校の下位が大学受験に失敗する理由/中学受験の前期入試で入学した悲劇/進学校で関関同立に合格できない悲劇」「進学校に入学しても落ちこぼれる最大の原因「中学・高校受験の優等生が高校の学習で落ちこぼれるか、克服するかの分岐点2つ」。
でも、下位校でもこのような高校の学習に適した学習に切り替えて成功する生徒も出てきます。
上位校の生徒が下位校の生徒に追い抜かれる理由2
上に書いたように自分の学習を変えれない生徒の原因は二つあると私は考えています。
ひとつは、中学時代の安楽な学習で成功した体験に固執して、高校で必要な思考力のいる厳しい学習には避けようとする姿勢です。小学校や中学校の時代はいうと親や塾の言うことをよく聞いていた生徒が、高校に入るとまったく言うことを聞かなくなることはとても多いです。私でも、塾で話し合った学習を守らずに自分勝手に宿題を開いて自分勝手に学習を進め、分からないところがあれば聞いて丸写しする上位高校の生徒は意外と多いです。
中学時代には反抗期もなく親塾に従って従順に学習していた子供が、高校に入って反抗期に入り本来の性質の怠け者丸出しになってしまい下位校で高校の学習に適応して真面目に学習している生徒に追い抜かれるのです。
最近の子どもの精神年齢の発育が遅く中学2年生の子供では小学校高学年の子供、高校生でも中学生を教えてるような気持ちになる事が塾ではよくあります。本来なら反抗期が中学時代に来て高校受験で失敗するところがまだ反抗期前で受験を従順に乗り越えて、高校で反抗期全開になって上位高校で落ちこぼれる子供がとても多い気がします「中学受験や高校受験で親が尻を叩かなければいけない場合、その親の努力は無駄になることが多い」。
中学時代に反抗期になって高校受験で失敗しても、それに気づいて高校で頑張ればいいだけです。でも高校で反抗期に入ると大学受験に失敗してジ・エンドです。こういう子供が最近進学校で増えていると感じています。
上位校の生徒が下位校の生徒に追い抜かれる理由3
一方でこの反抗期の遅れ=成長の遅れと逆のパターンも見受けられます。生育が早くその年齢なりの学習の吸収も容易で中学では優等生だった子供が、年齢が上がるに従って生育が遅かった子供に追い付かれ、その子供本来の能力のキャパシティの争いになる高校で逆転されるということです。
このことは中学受験をされた親御様ならよくご存知のことだと思います。幼くして受験をする中学受験では、早生まれと遅いまれの子どもの成長差による影響はとても大きいものです。高校受験ならそういう影響は少ないのではないかと考えられる方も多いと思いますが、東京大学の調査によると早生まれと遅生まれの子供には高校入試レベルで4.5の偏差値の差があるということが統計的に分っています。偏差値4.5というのはワンランク上と下の高校レベルに相当します。もちろんこの格差というのは成熟するに従って縮まって来ます。だから、高校受験でついていた差が大学受験では小さくなるというのは当然の話です「早生まれの学力不利益/学歴差は就職差になり所得差にもなる」「子作りは欲求にまかせて、子供には欲求を我慢しろという中学受験/早生まれを無視する親たちの中学受験」「成績目的で就学年度まで遅らせるアメリカ/早生まれで不利な中学受験をして、進学校で落ちこぼれて、現役志向と言う日本の不思議。」「浪人の薦め/早生まれの子供には中学受験より浪人を!」。
理由を並べるのではなく、解決策を出さないのはダメな塾だ!という方へ
上に書いてきたように高校での学習というのは子どもの将来の性質・発育・能力に大きく依存します。中学受験で親が押さえ込んでなんとか学習させているというような暗記主体の学習方法では理解力が必要な高校では学力は身につきません。また、親や塾が押さえ込んで何とか高校・中学受験で成功させたとしても、思春期で本性が丸出しになる高校や中学では親や塾が押さえ込めなくなり、結局は元の木阿弥になります。
だから将来の進路や就職などの話をして子供に気づかせようとするのですが、進学校で反抗期も相まっておごり高ぶっている子どもでは「エリートのオレに何を説教をしてるねん!」というようなことになりますし、進学校で落ちこぼれている生育の遅い子供では将来の話をしたところ「それで、なんっすか?勉強はイヤヤねん」と考えるだけ目の前の安楽な学習と楽しいクラブ活動がすべてです。
中学生の子供ならまだ塾でも押さえ込んで学習させることはできます。けれども高校生では無理です。だから高校生の場合、入塾段階で上に書いてきたような話をして納得して塾で頑張るという子供しかミドリゼミでは受け入れません。当塾のこのような方針を指導力不足というのなら来ていただかなくて結構です。