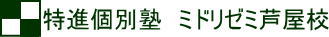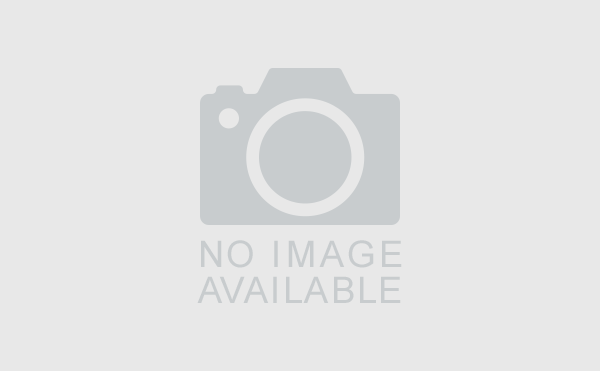中学生の国語の学習方法
国語の学習方法が分からない中学生に
英語や社会のように何をおぼえればいいのかは明確でなく、理科や数学のように何を解けばいいのかも明確ではない国語の学習は何をすれば良いのか分からない人が大半ででしょう。できることと言えば、準拠問題集をやったり、漢字をおぼえたり学校のノートを見たりするしかないでしょう。
でも国語の授業は明確な方針によって行われているということをご存知でしょうか?私はご存知だった親御さんそして生徒を見たことはありません。
国語の授業というのは、各セクションの最後に載っている「学習の手引き」などと記載されている内容に沿って行われています。この学習の手引きには各学年で学習しなければいけない内容がまとめられています。そして、各文章や作品は、この内容を学習できるものとして選択されているわけです。
この学習の手引きの内容とは?
文章を客観的に分析して作者の意図を正しく知る訓練として、各学年に相応しい内容が書き込まれています。国語の読解力とは読者の好き勝手な感想を持つことではなく、作者が何を意図して書いたのか正確に読み取る学習です。
でも、そんな抽象的なことを言われても学校の先生も困りますよね。だから、国語の教科書には何を教え学習すべきかがちゃんと書き込まれているんです。
「学習の手引き」を見直す
国語の先生が教科書の出版会社から購入したり、あるいは配られたりする学習の指導書もうこの学習の手引きに沿って作成されています。学校の先生のノートを読めば、学習の手引きに沿って授業が行われていることがわかるはずです。
いかに国語の先生でさえ、各文章だけから、授業など組み立てられません。他の教科とは違い、教える内容や問題が明確なわけがないのですから。
だから、準拠問題集もこの学習の手引きに沿って問題を作られていることが多いはずです。
もちろん、定期テストもこの学習の手引きを中心にした出版社の学習指導書や準拠問題集を参考に作られます。授業内容と同じく、国語の問題を一から考え、適切な解答を自信をもって準備できる教師など多くはいないからです。
だから、学習の手引きを見ながら学校のノートを復習すれば多くのことは解決します。もちろん学習の手引きに乗っていても学校のノートに記載されていないことがあります。そういう場合は市販されている教科書ガイドを見れば載っています。
このことが分かっていない塾が「読書」と言い出す
この学校の授業と教科書の学習の手引きとテストの関係を分かっていない塾では「読書」というような馬鹿げた学習が提案されます。文章を客観的に分析して作者の意図を正しく知る訓練が国語です。主観的に読んで、「私はこう思う」や「主人公はこう感じている」と楽しむ読書とは違います。国語教育の第一の目的は、仕事の書面や保険や契約の証書を客観的に文章内容を理解して、誤った人生を送らないように知るためです。読書のお楽しみのために税金を使っているわけではない。社会を発展させ維持していくために税金は使われます。
だから、「読書好きの文学少女は国語の成績が悪い・・・では解決策は?」「国語の学習の基本 読書とは違う」の通り、読書などでは国語の成績はあがりません。クラスに一人ぐらいいる読書好きの生徒の国語の成績が良くないことが多いのはその証です。
このことすら分かっていな教育関係者が多いのは、驚くべきことだと思います。
問題集を使っているだけの塾も要注意
教科書も教えずに塾用の国語の問題集だけ使って、その解説と解答を板書しているだけのような塾も要注意です。
確かに、問題集を使っても国語の学力は上がるでしょう。でも問題集の解説を読み上げるだけのような教師に国語の学力を上げられるはずはありません。そして最も大切なことは、数学のように論点が明確な学習でさえ把握することができない中学生の年齢で、国語の不明瞭な論理構成や論点を学習で理解することはできません。だから問題集でいくらその論理構成や論点を説明できたとしても、教科書ではそのポイントを把握することはできないのです。
だから教科書そのものを使って「ここはこうなっている」と直接説明する必要があるからです。しかし、そんなことをしている塾は見たことがありません。教科書には解答や解説がなく授業がやりにくい上に、校区が違う生徒がいる塾では教科書も違うことがあるからです。
でも語彙能力と情報量は読解力に必要
じゃあ、読書は全く必要ないのか?と言うとそうではありません。特に小学校時代の読書は必要不可欠です。でもそれは読解力のために必要なのではなく、語彙能力を確保するために必要なのです。
最近では中学生ばかりではなく高校生でも基本的な語彙能力がなく、読解力の前に文章が読めない子供が増えています。こうなってしまっては、塾でいくら教えても無理です。中学生の段階で落ちこぼれていると考えていいと思います。
毎回毎回、読解の前に語彙までいちいち噛み砕いて教えていては、学習など進みません。、毎回毎回小学生の四則計算や単位計算を教えながら方程式や関数の応用問題を教えるのに等しく無理です。
だから、「学校推薦図書」のような面白くもない本を無理やり読ませて、子供が嫌がって読書嫌いになってしまうというのは本末転倒です。子供が面白いと思う本、漫画でも雑誌でもいいから、を読ませて、分からない言葉があれば親に聞いてくるくらいの興味を引き出してあげることが肝心です。
特に中学受験せずに、放っておけば教科書さえ読まない児童には絶対必要なことです。公立中学で通知簿3がついて終了です。そもそも国語の読解力をつけるステージに上がって来れないですから「公立中学の下半分は終わっている」「公立中学通知簿3と4の差」「境界知能とグレーゾーンの子供に公立中学では通知簿3がつく?」「公立中学通知簿3の学力は、塾では共有されている」。