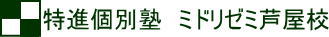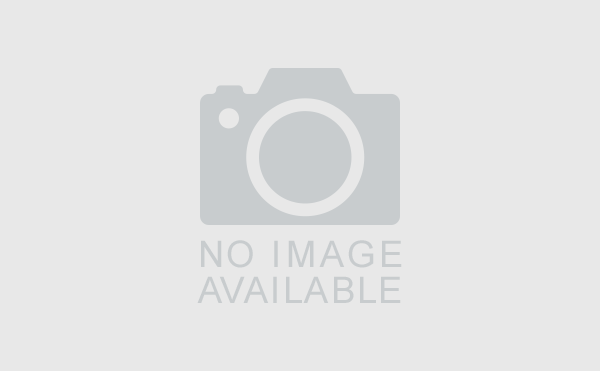進学校で失敗する生徒のまとめ/種類別
一番多いタイプ:高校の学習に入っても中学生気分で落ちこぼれる
「進学校の1/4は中学2年生で落ちこぼれる/国立大学など行けない」などでも散々書いてきましたが、中高一貫私立の進学校の多くは中学2年生から高校の数学、中学3年生から高校の英語を進める学校が一般的です。この表では難関中高一貫校は中2の後半から高校の学習が始まるようになっていますが、府県トップレベルの進学校では中二の最初から始まります
学校側にすれば、進学校に進む能力がある子供なら中学レベルの学習は2年ほどで終えても落ちこぼれないし、高校の学習を1年以上前から進めれば大学入試の1年以上前にカリキュラムが終わって1年以上大学受験勉強に専念できるという計画です。

ところが、これがうまく機能しない事が多い。最も多い理由はまだ中学生の生徒が、段違いに難しい高校の学習が始まる準備なしにそのまま突入して行って落ちこぼれるというパターンです。理由は明確で、まだ中学生の制服を着て中学に通い、依然と同じ校舎のまま、クラブ活動も同じで、教科書だけが変わるからです。
教師の方も、「これからは高校の学習が始まるから今までとはまったく違う。予習などの準備をきちんとして臨まないと落ちこぼれる。」と生徒に指導しないからです「新高校生の新学期の開始/数学の予習を!」「新高校1年生は英語の予習も今から始めよう/頭から英語が読めるようになろう」「高校生の学習/予習で分かる大学進学ランク」。
この準備が出来ていない状態で、ただでさえ難しい高校の学習を、年齢不相応に脳もまだ高校生並みには発育していない中学生にねじ込むのです。落ちこぼれて当然と言えば当然なのです。
二番目に多いタイプ:能力不足または発育が遅い
二番目に多いタイプは、このような早い学習に能力不足からついていけない生徒が落ちこぼれるというものです。具体的には、丸暗記主体の中学受験で、親が尻を叩いてなんとか進学校にもぐり込んだような生徒が多いです。
中学の学習は理解力も応用力もそれほど必要ではなくこの丸暗記で何とかなるのですが、高校の学習特に数学となると丸暗記だけでは対応ができなくなります。理解力や応用力が必要になります。ところがこの力がない生徒が学習塾で効率的な丸暗記学習をして中学受験で進学校に入ってきます。そこで、高校の学習に入った時に落ちこぼれます。
あるいは発育の遅い生徒も同様の傾向が見られます。例えば中学2年生といっても小学校並みの体格や雰囲気を持った子供です。体の発育が遅いのに脳の発育だけ人並み以上に発達していて高校の学習を受け入れられるということはありません。こういうタイプの生徒でも落ちこぼれていることが多いです。
もちろん例外はあります。天才型で理数系科目に人並み以上の能力を発揮する生徒です。こういう生徒は中学受験で親などが教える必要もなかったでしょう。数学も丸暗記してというより感覚的になんとなく解いていたはずです。こういう理数系に才能を発揮する生徒でも見た目は幼い場合が多いです。
こういう生徒は巻き返しが効くのか?・・・大抵は無理です
最初に書いた「中学生気分が抜けきらない生徒」が心機一転して、あるいは2番目に書いた生徒が人並の発育に追いつてくる高校になって、巻き返しが効くのか?
私の経験では、残念ながら多くの場合は難しいです。
というのも上の表からお分かりのように、中高一貫校ではもうすでに高校の学習の半分が終わっています。今までの高校の学習内容の上にさらに学習内容が積み重なり学習の難易度は上がっていきます。優秀な生徒でもその状況に精一杯なのに、基礎学力のない生徒が気持ち切り変わった、生育が追いついたからと言って過去学習をやり直して、そして今現在他の生徒がやっている学習に追いつくのは難しい。単純に考えても倍の学習時間が必要です。順調に学習している生徒でさえ頑張っているのに、その生徒の倍の時間を学習するなど物理的に時間が取れません。能力以前に不可能なのです「中学受験と高校受験の弊害/進学校に中位・下位で入るのは愚かです」。
その上、上位の進学校でも能力差は大きいです。上位の進学校の中上位の生徒は一を教えれば十を解くことができます。だからこんなめちゃくちゃな授業速度についていっているのです。一方上位の進学校でも並みの生徒=は最上位の公立高校に進むような生徒は、一を教えれば一を知る能力がありますが、能力的には明らかに差があります。だから追いつくのは難しい場合が多い。
それに、この一を教えれば十を知る生徒なら、それほど頑張らなくても落ちこぼれるまでは成績は落ちません。それなら巻き返しは効きます。「「中学受験と高校受験の弊害/進学校に中位・下位で入るのは愚かです」。
そして、一を教わって知る生徒でも、その一を積み上げていく努力が出来る生徒なら、最上位は取れなくても神戸大学あたりのラインで落ちつき、落ちこぼれることはありません。そういう地道な努力をできないから落ちこぼれているのです。中学受験ではまだ親の言うことを聞いて丸暗記をがんばり何とか進学校に入れたのでしょう。でも、怠け者の本性丸出しになった思春期ではもう親の言うことは聞きません。親が過去の幻想にしがみついてイメージしているイイ子ではなかったのですが、親はいつまでも「うちの子は本当はイイ子なんです。塾で言ってもらえれば、適切な指導がされれば大丈夫なはずです!」と塾に言ってきます。でも、塾の判断は「そら、小学校では親の言うことを聞いたかもしれんけど、実際はだらしない、ヤル気もない子どもだったんやな」と言う正反対の結論です。
そして、こういう子供に塾が一生懸命指導しても、たいていは受け流されます。矯正しようと周囲がヤキモキしている間に時間は過ぎて学校の授業はどんどん進み、子供が年齢的に成長し思春期も終わった高校生後半になって「ヤバイ」と自分で気づく頃になっては、とっくに手遅れになっていることがほとんどです。そのことを塾は多くの子供の指導経験から知っています。でも親の目に映るのは「特別な我が子だから、何とかなるはずだ。この子は本当はイイ子なのよ!」です。ご期待に添うのは無理ですよ。
そして、こういう進学校で落ちこぼれていてる子供でもプライドだけは高い子供も多く、高校の授業は終わり周囲は受験勉強を始め目の前には大学受験がぶら下がっている時期にもかかわらず、「じゃあ、英国社に絞って関関同立」と判断できずに、「今からチャート式の数ⅠAをやり直して、最低でも神戸大学!」なんて言うことも多い。それなら、誰が教えても無理ですよ。学習の前にやっぱり脳ミソが足りないんです。
しかも、こういう供では「私が悪かった。浪人してでも取り返す!だからこの1年間はここまでやる。協力して欲しい。」って根性も知力ないでしょ?だから無理です。
こうして落ちこぼれた生徒への対策
こうして落ち込ぼれた高校生を親が塾に連れて来て、多くの場合言うことが「学校の成績を上げて欲しい。せっかく進学校に入ったのだから」と言います。でもそれは上に書いたように難しい。
だからミドリゼミでは状況を説明して、「「もう学校の成績を追い求めるのはやめて、入試に必要な教科の学習を基礎からやり直しましょう。塾の体験授業で分かったように基礎から出来ていないじゃないですか。お子さんに合った学習をしましょう。」と提案します「数学が苦手な生徒の勉強方法/数学を捨てることです」「高校生の数学 1年でつまずく生徒」。
しかし、「せっかく進学校に入ったのに関関同立?神戸大学も無理なの?」と反発する方も多いです。進学校の看板を考えるともっともだと思います。でも、その進学校内での現状はもっともではないからこんな嫌なことを言っているわけです。
「だったら、クラブ活動も辞めて、遅れを取り戻し、そして今の学習を進めるために他の生徒の倍学習して下さい」と言うと、「クラブ活動は続けたい」だの「そこまでするのはこの子が可哀想」などと言い始める方が多い。
その甘い考えだから落ちこぼれていることも親子で分かっておられないので、もうこの時点で無理です。
こうならないために
「中高一貫校の生徒は、高校の数学にカリキュラムが入る前に来てください」
以上です。