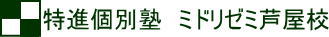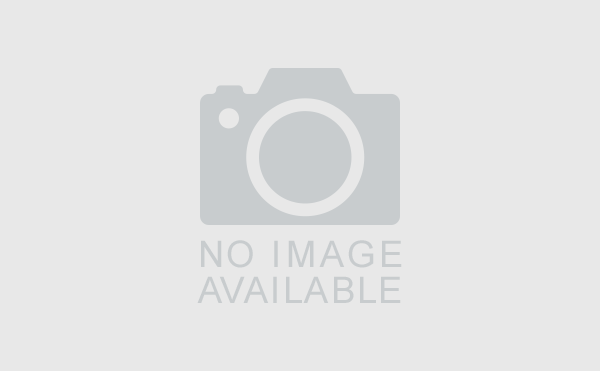中間テストの反省をしよう/高校と中学の数学の学習の違いが分からないと失敗する/並の進学校の下位だと関関同立は無理
この話のそもそもの前提/反省しても無駄な生徒・反省が出来ない生徒はこの時点で無理
ここでこれから書くのは、キチンと授業を聞き、「ここはこうなっているんだ。」と考え、復習する生徒のお話です。公立中学なら通知簿4の上半分以上です。上位3割が神戸大以上というソコソコの進学校なら真ん中上の生徒の話です。
それ以外の生徒は中学の段階でつまずいていますから、進学校の中学三年あるいは公立高校の一年生で高校の学習範囲に入ってから反省したところで無駄だからです。
無駄な理由は二つです。そもそも能力的に中学の学習が出来ない。この場合、高校の学習など不可能です。公立中学で、通知簿3以下が該当します。「親が知らない公立中学通知簿3と4のレベルとは?/中学受験は必須」「中学1年生の計算問題で分かる「もうダメ」な生徒/でも公立中学通知簿3のデフォルト」「公立中学の通知簿3は、教えるのが無理になってきている」
次に、通知簿4の下半分では、ダラケ切っていて中学の学習でもいい加減なことをしているのに高校の学習でキチンとするなどありません。「そこを変えるのが塾でしょう?」って言われても、中学時代も散々失敗してきたはずです。それでも考えを改めずに、入試前にやっとやる気になって少し成績を伸ばして中堅公立高校に進んだ生徒など、それが成功体験になって高校では余計にひどいことをやりだします。中堅高校程度に進んだことを反省もせずに成功体験と捉えて増長しているのですから、塾アドバイスを聞き入れるというようなことなどありません。「中学3年の冬休みまで本気を出さない子供たちの将来」
だから、ここで高校の学習について書いていくのは、中学でキチンと学習できていた子供に関してです。公立高校では通知簿が4と5で埋っている、中高一貫のソコソコの進学校なら上半分の生徒に関してです。
優等生が高校で陥る学習不足
このレベルの生徒では中学の学習範囲伊など理解に難しいほどの学習ではなく、宿題の問題集でもして確認しておけば十分です。だから、中高一貫校では中学三年分の学習を二年間で終えて中学三年からさっさと高校の学習に進みます。特別な指導など必要ありません。だから、公立中学の優秀者を相手にする進学塾などでは、学校の授業とさほど取らないと通り一遍の予習を進めるようなバカな授業をするのです。そんないい加減な授業をしても生徒頼みで成績は維持できるからです。「中学生に予習と大量の宿題は不要/進学塾の都合だけです」「進学校や進学塾に素晴らしい授業や進路指導があるという誤解」「進学校や進学塾への誤解/何度も書いてきたことですが・・・」
ところが、こういう子供でも、高校の学習は難しく落ちこぼれることが多くあります。その多くの理由は、中学の学習の成功体験から、同じように高校の学習にアプローチするからです。特に数学の学習でつまずいて全教科に悪影響を及ぼすことがとても多いです。
リ理由は、高校の学習、特に数学は難しくなるからです。中学の学習で「フンフン、そうか」と授業で理解できて問題集もパッとできた子供でも、高校の学習では「そうか」と理解できても、いざ独力で問題集を解くとまるっきりできないことが普通です。神戸高校や市立西宮など上位で「神戸大学行ける?」と言うレベルでもそれが普通です。京都大学や国公立の医学部に進むような特殊な学習適性を持つその上のレベルだけが、中学時代と同じく「フンフン、そうか」で進めます。
だから、ほとんどの子供が「そうか」と理解してから、悪戦苦闘して独力で問題を解き切って「出来る!」までの努力と時間が必要なのです。ところが、高校の授業進度は早く、中学の時のように「フフン」で終わっていたらテストで大失敗することになります。キチンと理解しようとすれば、学校の宿題で復習をしたりしている間に、授業はドンドン先に進まれて追いつけなくなります。それで、「これはマズい」と言う状態になった頃には、授業ははるか先に進まれてにっちもさっちも行かなくなる。
難しく時間がかかる数学にあたふたしている間に、英語や古文などもしっかり勉強できなくなる。定期テスト前にも主要教科の学習が積み上がって理科や社会ができない。結局全部中途半端になって全体的に成績が下がります。これがほとんどの高校生で見られる現象です。
その結果、国公立大はムリ、関関同立もヤバい
数学が出来ていないと国公立大学は無理です。共通テストもあるし、文系でも二次に数学があります。授業や学校の問題集程度のレベルで困っているようでは、文系でも国公立はムリです「数学が不得意な生徒は、文系でも国立大学は不可能」。
だから、数学が苦手な高校生の場合、「数学を学習しない!その分英語や古文をキチンと学習して関関同立に行く!」と私立文系で割り切ればいいのですが、ほとんどの優等生では国立大学への希望をあきらめずに中途半端に数学に手を出して、上に書いたように肝心な英語にまで悪影響を及ぼしてしまいます。これは、優等生が集まる進学校で非常に多い。だから下半分の生徒では、英語と古文だけでもまじめに勉強しておけば行けた関関同立にも行けなくなるのです。
この状況は兵庫県のトップの公立校、進学校として名前を轟かせている私立、六〇や白〇、海〇などで実際に起こっていることです。進学実績を見れば明らかでしょう。神戸高校でも上位3割ほどで神戸大学、真ん中で関関同立なんですから。下位だと産近甲龍がやっとです。
だから、高校では高校に則した数学の学習をしましょう
この状況を克服して国公立大学に進むためには、徹底的に数学の予習をして、学校の進度との間に大きな余裕を作っておくことです。そうすれば英語をはじめ、他教科の復習も十分できます「春休みには数学の予習を半年分やる!/その予習が必要な生徒とは?」「新高校生の新学期の開始/数学の予習を!」。
そのために春休みに半年分、夏休みに半年分の予習をやるのです。自分で考え、自分で問題を解く時間がかかる学習を、十分に時間が取れる長い休みの間ににやっておく。これが、普通の優等生が国公立大学に進む唯一の方法です。
ただ、ほとんどの優等生はこのような学習をしません。やはり遊ぶことを優先します。だから進学校でも7割の生徒は神戸大学以上の国立大学に行けないのです。
上位国立大学に進める条件
上位の国公立大学には「勉強ができる」だけでは行けません。
私の経験では余裕で関関同立に合格できる生徒と神戸大学に合格する生徒の間には、能力的にはそう大差はあると思いません。両者の違いは、自分が好きなことでも我慢して努力できるという資質の差です。長い休みの間でも確実に努力していけるという資質の差です。
上に書いたような厳しいアドバイスを受けられる塾・環境、それを理解し受け入れられる資質、そして厳しい学習計画を遂行できる根性、この3つが揃っていないと行けません。